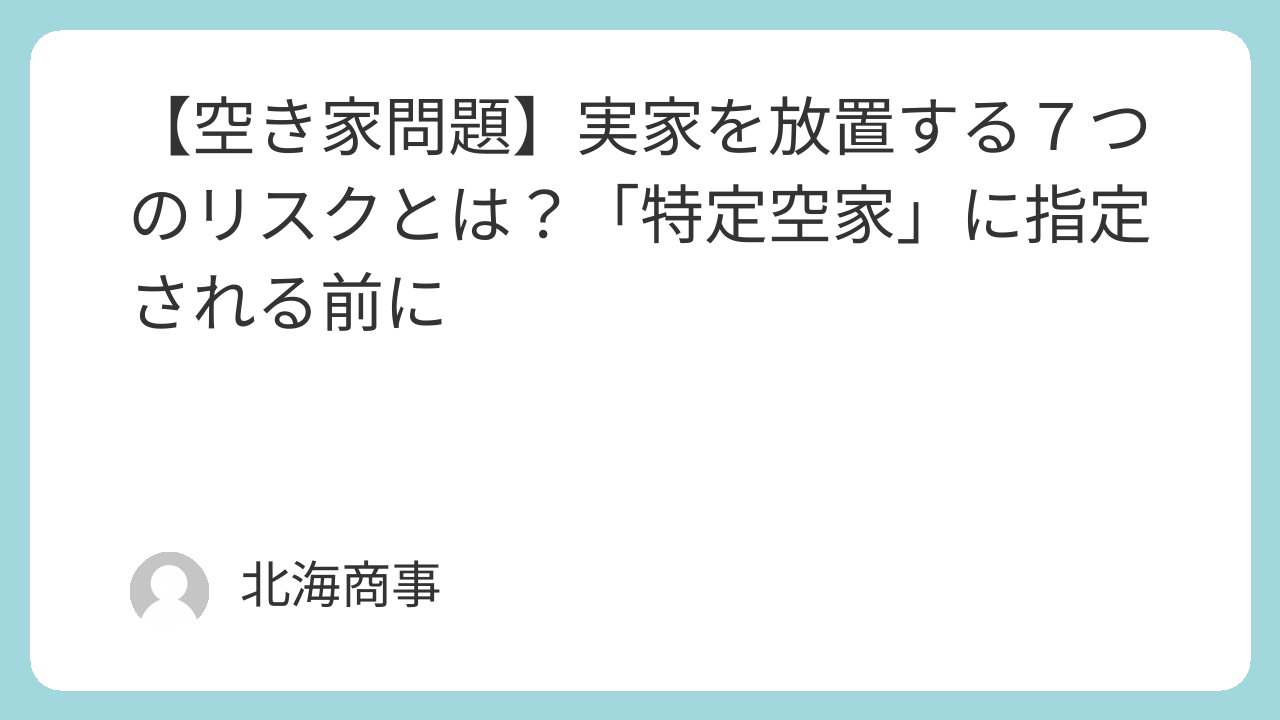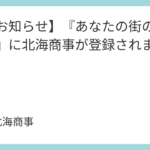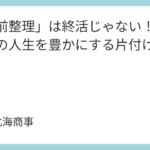親から相続した実家が空き家で、放置するリスクや『特定空き家』という言葉に不安を感じています。金銭的・法的リスクや指定回避策を知り、大切な資産を守りたい。空き家放置は本当に深刻な事態を招くのでしょうか?

ご不安なお気持ち、よく分かります。空き家の放置は、固定資産税増額や賠償責任など深刻な事態を招くため、早期の対策が不可欠です。この記事では具体的なリスクや『特定空き家』回避策を全て解説し、お客様の資産を守るための知識を提供します。
親から相続した実家が空き家になっており、放置するリスクや「特定空き家」という言葉に不安を感じていませんか?この記事を読めば、空き家がもたらす具体的な金銭的・法的リスクから、「特定空き家」への指定を回避する方法まですべてが分かります。
結論として、空き家の放置は固定資産税の増額や倒壊による賠償責任など深刻な事態を招くため、早期の対策が不可欠です。あなたの資産を守り、将来のトラブルを防ぐための知識がここにあります。
1. なぜ空き家を放置してはいけないのか?その根本的な理由


実家が空き家になり、『いつか使うかも』『解体費用が…』と放置しがちです。でも、多くのリスクがあると聞き、個人の問題だけではないと知り不安です。なぜ空き家を放置してはいけないのか、その根本的な理由を教えてください。

お気持ちは大変よく分かります。しかし、空き家放置は所有者様自身だけでなく社会にも多くのリスクをもたらします。ここでは、なぜ放置してはいけないのか、大切な資産と皆様の安心を守るため、その根本的な理由を掘り下げて詳しく解説します。
実家や相続した家が空き家になったものの、「いつか使うかもしれない」、「解体費用がかかる」といった理由で、つい放置してしまっている方も少なくないでしょう。しかし、空き家を放置することは、所有者自身が考える以上に多くのリスクを伴い、もはや個人の問題ではなく社会全体で取り組むべき課題となっています。
なぜ空き家を放置してはいけないのか、その根本的な理由を掘り下げていきます。
1-1. 日本の空き家問題の現状
日本の空き家は年々増加の一途をたどっており、深刻な社会問題となっています。総務省統計局の「住宅・土地統計調査」によると、2023年時点での全国の空き家総数は約900万戸にのぼり、総住宅数に占める空き家率は13.8%と過去最高を更新しました。
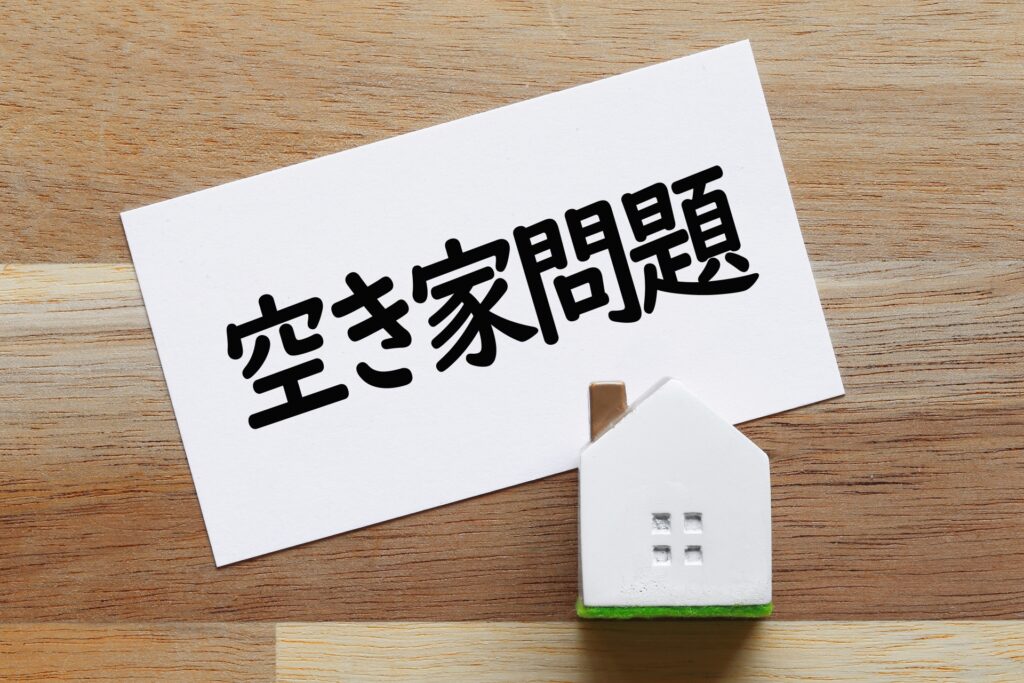
これは、日本の住宅の約7戸に1戸が空き家であることを意味します。 特に、活用予定のない「その他の空き家」が385万戸と増加傾向にあり、これが様々な問題の温床となっています。
人口減少や高齢化がさらに進む日本では、この問題は誰にとっても他人事ではありません。
日本の空き家数と空き家率の推移
| 調査年 | 空き家数 | 空き家率 |
|---|---|---|
| 1993年 | 448万戸 | 9.8% |
| 2003年 | 659万戸 | 12.2% |
| 2013年 | 820万戸 | 13.5% |
| 2023年 | 900万戸 | 13.8% |
1-2. 空き家が地域に与える悪影響

適切に管理されていない空き家は、様々な形で地域社会に悪影響を及ぼします。まず懸念されるのが、防災・防犯上のリスクです。老朽化した建物は地震や台風で倒壊する恐れがあるほか、放火のターゲットにされたり、不審者の侵入を招いたりと、地域の安全を脅かす存在になり得ます。
さらに、ゴミの不法投棄や害虫・害獣の発生といった衛生問題、雑草の繁茂や建物の破損による景観の悪化も深刻です。
問題は近隣住民に直接的な被害や不安を与えるだけでなく、地域全体の不動産価値の低下にもつながる可能性があります。
1-3. 国が対策を強化する理由

こうした状況を受け、国も対策を強化しています。その中心となるのが2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。 この法律は、国民の生命、身体又は財産の保護、そして生活環境の保全を図ることを目的としています。
法律によって、行政が空き家の実態調査や所有者への指導・勧告、さらには強制的な措置(行政代執行)まで行えるようになりました。 2023年には法改正が行われ、倒壊などの危険性が高い「特定空家」になる前の段階である「管理不全空家」の区分が新設されるなど、より早期の段階から対策を講じる姿勢が鮮明になっています。
これは、国が空き家問題を個人の財産管理の問題としてだけでなく、社会全体の安全と利益を損なう重大な課題と認識していることの表れです。
2. 所有者が背負うことになる7つの空き家リスク


相続した実家が空き家で、放置している状態です。単にもったいないだけでなく、所有者には様々なリスクが降りかかると聞き、不安です。お金、安全、行政の側面から、具体的にどのようなリスクがあるのか教えてください。

ご不安なお気持ち、お察しいたします。空き家の放置は、所有者様に金銭的、安全面、行政上の深刻なリスクをもたらしかねません。大切な資産を守り、将来のトラブルを防ぐため、所有者様が背負うことになる7つの具体的なリスクを詳しく解説します。
2-1. お金に関するリスク
空き家を放置することで、まず直面するのが経済的な負担です。活用していないにもかかわらず、税金の支払いや資産価値の低下といった形で、着実に家計を圧迫していきます。
2-1-1. 固定資産税の負担増
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で6分の1に軽減されています。しかし、管理不十分な空き家が「特定空き家」に指定され、自治体からの改善「勧告」を受けると、この特例から除外されてしまいます。
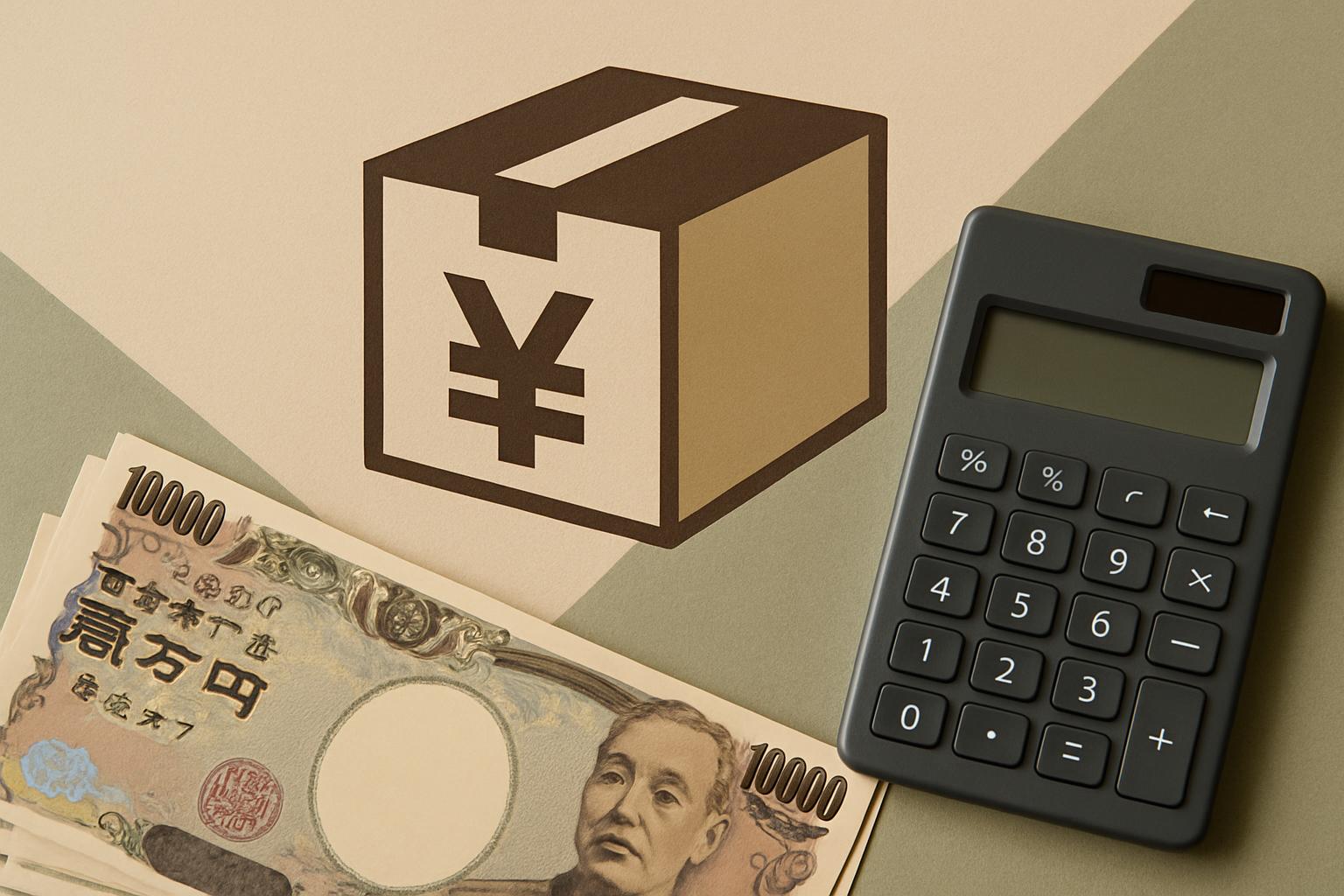
その結果、翌年度から土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。
また、都市計画区域内に不動産がある場合は、都市計画税も最大3倍になるため、税負担はさらに大きなものとなります。
2-1-2. 資産価値の目減り

老朽化が進むと建物の利用価値は失われ、いざ売却しようとしても買い手が見つからなかったり、解体費用を差し引くと手元にお金が残らないケースも少なくありません。
適切な管理を怠ることで、大切な資産が「負の遺産」に変わってしまうリスクがあるのです。
人が住まなくなった家は、換気不足による湿気やカビ、雨漏り、害虫・害獣の発生などにより、驚くほど速いスピードで劣化が進行します。
2-2. 安全に関するリスク
空き家のリスクは、所有者自身の問題にとどまりません。建物の倒壊や火災など、近隣住民の安全を脅かし、多額の損害賠償を請求される事態に発展する危険性もはらんでいます。
2-2-1. 倒壊・破損による賠償責任
老朽化した空き家は、台風や地震などの自然災害によって倒壊するリスクが高まります。

もし、屋根瓦や外壁が落下して通行人にケガをさせたり、隣の家を破損させたりした場合、その損害賠償責任は所有者が負うことになります。
これは民法第717条の「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」に基づくもので、たとえ自然災害がきっかけであっても、管理不備が原因とみなされれば責任を免れることは困難です。
2-2-2. 火災・犯罪の発生源
人の出入りがない空き家は、放火のターゲットにされやすい傾向があります。 敷地内にゴミや枯れ草が放置されていると、さらにリスクは高まります。
また、不法侵入や不法占拠、薬物の取引場所など、犯罪の温床となる可能性も否定できません。 空き家が地域の治安を悪化させる原因となり、近隣住民に多大な不安を与えることになります。
2-3. 行政に関するリスク
空き家の放置を続けると、最終的には行政による介入を招きます。助言や指導から始まり、最終的には強制的な措置に至るまで、段階的に厳しい対応が取られることになります。
2-3-1. 特定空き家への指定
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、倒壊の危険性が高い、衛生上有害である、景観を著しく損なっているなど、放置することが不適切と判断された空き家は「特定空き家」に指定されます。

これは、行政からの最終警告ともいえる措置であり、この指定を受けると、後述する固定資産税の増額や過料といった、より具体的なペナルティの対象となります。
2-3-2. 改善命令と過料
特定空き家に指定されると、まず自治体から状況を改善するための助言や指導が行われます。 それでも改善が見られない場合は「勧告」、さらに「命令」へと措置が強化されます。
そして、所有者がこの命令に従わない場合、50万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
2-3-3. 行政代執行と費用請求
改善命令にも応じず、危険な状態が続くと、行政が所有者に代わって建物の解体などを行う「行政代執行」が実施される場合があります。

ここで最も注意すべき点は、解体にかかった費用(数百万円に上ることもあります)は、全額所有者に請求されるという事実です。
費用の支払いができない場合は、給与や他の不動産など、財産の差し押さえが行われる可能性もあり、所有者にとって最も重いリスクと言えるでしょう。
3. 「特定空き家」とは?指定を回避するための知識


空き家を放置すると行政から『特定空き家』に指定される可能性があると聞き不安です。その定義や、指定された場合のリスクについて詳しく知りたいです。指定を回避するための具体的な知識を教えていただけますか?

ご不安なお気持ち、お察しいたします。『特定空き家』は周辺環境に悪影響を及ぼす危険な状態と判断され、指定されると様々なリスクが伴います。この章では定義や具体的なリスクを詳しく解説し、回避するための知識をお伝えします。
空き家を放置し続けると、行政から「特定空き家」に指定される可能性があります。
これは「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく措置で、単なる空き家とは異なり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす危険性が高いと判断された状態を指します。特定空き家の定義や指定された場合の具体的なリスクについて詳しく解説し、指定を回避するための知識を身につけていきましょう。
3-1. 特定空き家の定義と判断基準
「特定空き家」とは、放置することが不適切な状態にあると市町村が判断した空き家のことです。 具体的には、「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、以下の4つの基準のいずれかに該当するものが指定対象となります。
これらの基準は一つでも当てはまれば指定される可能性があるため、所有する空き家が該当しないか確認することが重要です。
| 判断基準 | 具体的な状態の例 |
|---|---|
| 保安上危険となるおそれ | 建物が傾いている、屋根や外壁が剥がれ落ちそうになっている、基礎に亀裂が入っているなど、倒壊や部材の落下のリスクがある状態。 |
| 衛生上有害となるおそれ | ゴミの不法投棄や放置による悪臭の発生、害虫や害獣の繁殖、浄化槽の破損による汚物の流出など、公衆衛生を害する状態。 |
| 景観を損なっている | 窓ガラスが割れたまま放置されている、建物全体が落書きで覆われている、庭の雑草が人の身長以上に伸び放題になっているなど、周辺の景観を著しく損なう状態。 |
| その他不適切な状態 | 不審者が侵入・滞在している、動物が住み着いて鳴き声や糞尿による被害が出ている、庭木が隣家や道路にはみ出して通行を妨げているなど、周辺環境に悪影響を及ぼす状態。 |
3-2. 指定された後の行政からのアプローチ
特定空き家に指定されると、行政は所有者に対して段階的に改善を促すアプローチを取ります。
最初は「助言・指導」という形で、問題点の指摘と改善策の提案が行われます。 これに応じず状況が改善されない場合、より強制力のある「勧告」が出されます。この「勧告」が、後述する固定資産税の増額に直結する重要な段階です。
さらに勧告にも従わない場合は、改善を強制する「命令」が出され、これに違反すると過料が科される可能性があります。最終手段として、所有者に代わって行政が解体などを行う「行政代執行」が実施されることもあります。
3-3. 固定資産税の増額とその他のペナルティ
特定空き家に対する最も大きなペナルティの一つが、固定資産税の大幅な増額です。通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で6分の1に軽減されています。

しかし、特定空き家として「勧告」を受けると、この特例の対象から外れてしまいます。その結果、土地の固定資産税が更地とほぼ同等になり、最大で6倍近くに跳ね上がる可能性があります。
さらに、行政からの「命令」に従わなかった場合は50万円以下の過料が科されることがあります。最終的に行政代執行が行われた場合、解体などにかかった費用(数百万円に及ぶこともあります)は全額所有者に請求されます。
4. 空き家リスクを解消する実践的アクションプラン


空き家がもたらす様々なリスクを回避するには、具体的な行動が重要だと理解しました。しかし、今後どうしたいのか、何から始めれば良いか迷っています。私の状況に合わせた最適な解決策とアクションプランを教えていただけますか?

ご安心ください。空き家の問題を先送りせず行動を起こすことは非常に大切です。ここでは、お客様の状況に合わせた最適な解決策を見つけ、大切な資産を守り、将来のトラブルを防ぐため、具体的な3つの選択肢とそのアクションプランを解説します。
空き家がもたらす様々なリスクを回避するためには、問題を先送りせず、具体的な行動を起こすことが重要です。所有している空き家を今後どうしたいのか、ご自身の状況に合わせて最適な解決策を見つけましょう。
ここでは、具体的な3つの選択肢と、それぞれのアクションプランを解説します。
4.1 現状を把握し方針を決める

まず最初に行うべきは、空き家の現状を正確に把握することです。建物の劣化状況、土地の境界、権利関係(相続登記が済んでいるかなど)を確認しましょう。特に、遠方に住んでいる場合は、記憶と実際の状況が大きく異なっている可能性があります。
現状を把握した上で、「売却して手放す」、「貸し出して収益化する」、「適切に管理して維持する」という3つの基本方針の中から、どれが最も適しているかを検討します。
方針を決める際には、立地条件や周辺地域の需要も重要な判断材料となります。例えば、駅に近い、あるいは商業施設の近くであれば賃貸の需要が見込めますし、地方の郊外であれば売却や管理に絞られるかもしれません。
複数の選択肢で迷う場合は、不動産会社などの専門家に相談し、査定を依頼してみるのも良いでしょう。
4-2. 【選択肢1】売却して手放す
空き家を今後利用する予定がなく、管理の手間やコストから解放されたい場合に最も有効な選択肢が売却です。売却してしまえば、固定資産税の支払いや、建物の老朽化、近隣トラブルといったすべてのリスクから解放されます。売却益を得られる可能性がある点も大きなメリットです。
売却方法には、不動産会社に仲介を依頼する方法のほか、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」や、自治体が運営する「空き家バンク」に登録する方法などがあります。 建物の状態によっては、解体して更地として売却する、あるいはリフォームしてから売却するといった方法も考えられます。
どの方法が最適か、不動産会社と相談しながら進めるのが一般的です。
4-3. 【選択肢2】貸し出して収益化する

資産として手放さずに、家賃収入を得たいと考えるなら、賃貸物件として貸し出す方法があります。毎月の安定した収入は、固定資産税などの維持費を賄うだけでなく、将来の私的年金代わりにもなり得ます。
また、人が住むことで家の換気が行われ、建物の劣化を遅らせる効果も期待できます。
貸し出し方には、一般的な戸建て賃貸のほか、複数の人で共有するシェアハウス、旅行者向けの民泊など、様々な形態が考えられます。 ただし、貸し出す前にはリフォームが必要になる場合が多く、初期費用がかかる点や、空室リスク、入居者トラブルの可能性も考慮しておく必要があります。
将来的にご自身で住む可能性がある場合は、契約期間を定められる「定期借家契約」を選ぶと良いでしょう。
4-4. 【選択肢3】適切に管理して維持する

将来的に住む計画がある、あるいはすぐに売却や賃貸の方針を決められない場合は、ひとまず適切に管理・維持するという選択肢があります。適切な管理を続けることで、資産価値の低下を防ぎ、特定空き家に指定されるリスクを回避できます。
また、いつでも売却や賃貸に移行できる状態を保てるメリットもあります。
管理方法としては、自分で定期的に訪れて清掃や換気、庭の手入れを行う「自主管理」と、専門の管理会社に委託する「管理委託」があります。遠方に住んでいる場合や、手間をかけたくない場合は、管理会社への委託が現実的です。
サービス内容は、巡回や簡易清掃、郵便物の整理などで、月額数千円から利用できるものもあります。
4-4-1. 各選択肢のメリット・デメリット比較
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 売却 | ・管理の手間やコストから完全に解放される ・固定資産税の支払い義務がなくなる ・まとまった現金収入を得られる可能性がある | ・資産を手放すことになる ・買い手が見つからない可能性がある ・売却価格が希望額に届かない場合がある |
| 賃貸 | ・家賃収入を継続的に得られる ・資産として所有し続けられる ・人が住むことで家の劣化を防げる | ・リフォームなどの初期費用がかかる ・空室になるリスクがある ・入居者とのトラブルが発生する可能性がある |
| 管理・維持 | ・資産価値の維持につながる ・特定空き家への指定を回避できる ・将来の選択肢(居住、売却、賃貸)を残せる | ・管理費用や固定資産税がかかり続ける ・収入は得られない ・定期的な手間がかかる(自主管理の場合) |
5. まとめ

実家など、思い入れのある建物を空き家のまま放置することは、多くのリスクを伴います。固定資産税の負担増や資産価値の低下といった金銭的な問題だけでなく、倒壊や火災、犯罪の温床となる安全上のリスクも無視できません。
特に、2023年に改正された空家等対策特別措置法により、「特定空家」に指定されると、税金の優遇措置が解除され、最終的には行政代執行に至る可能性もあります。なぜなら、空き家は個人の問題だけでなく、地域社会全体の安全や景観を損なう社会問題と認識されているからです。
手遅れになる前に、売却、賃貸、適切な管理といった選択肢の中から、ご自身の状況に合った最適な方法を見つけ、早期に行動を起こすことが何よりも重要です。