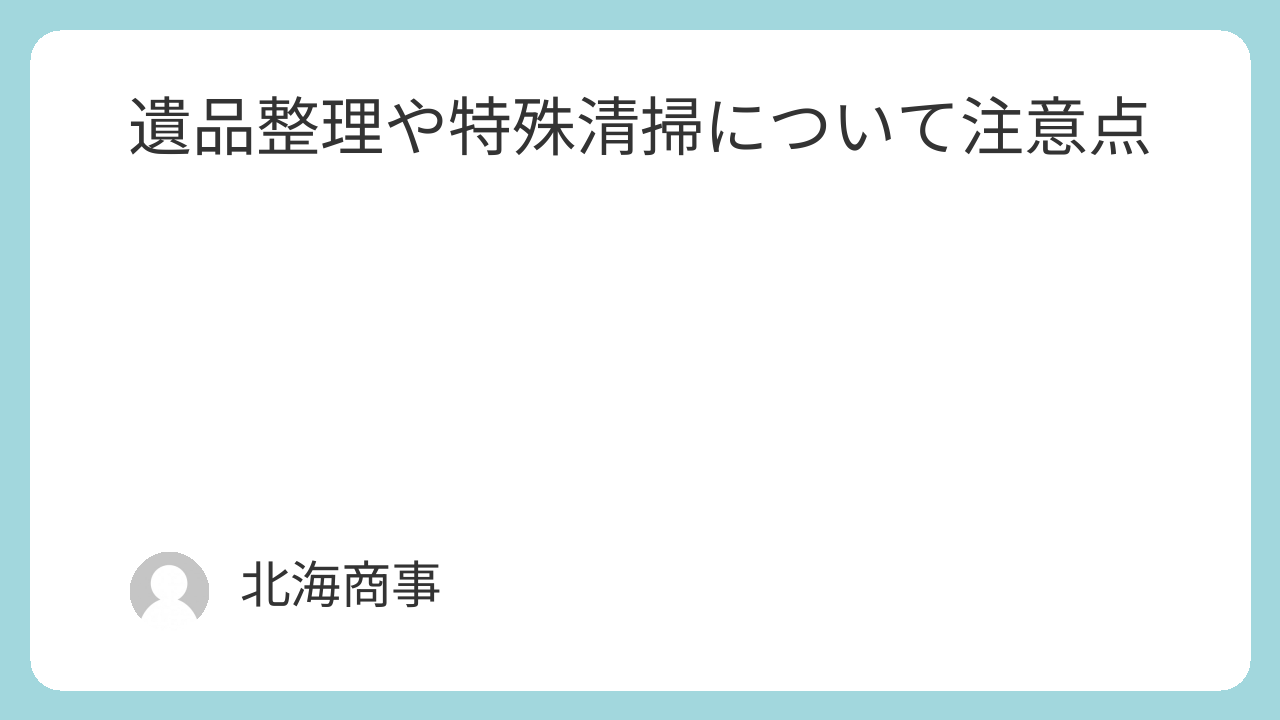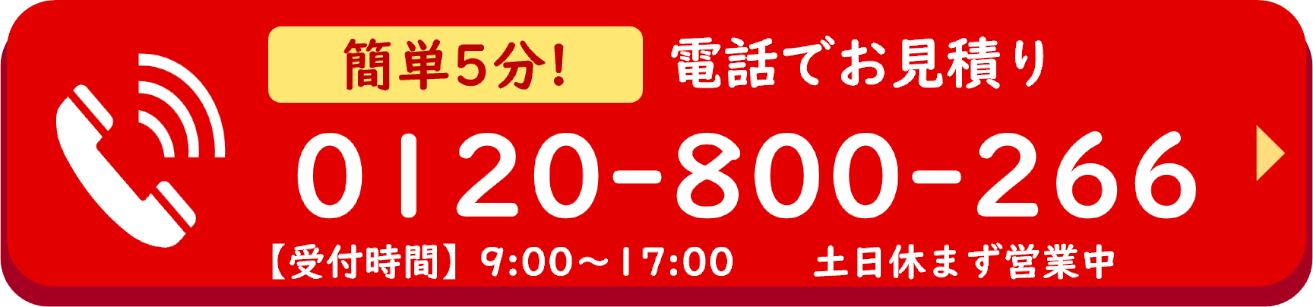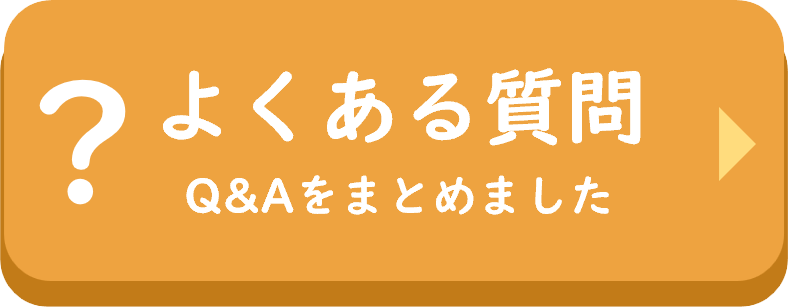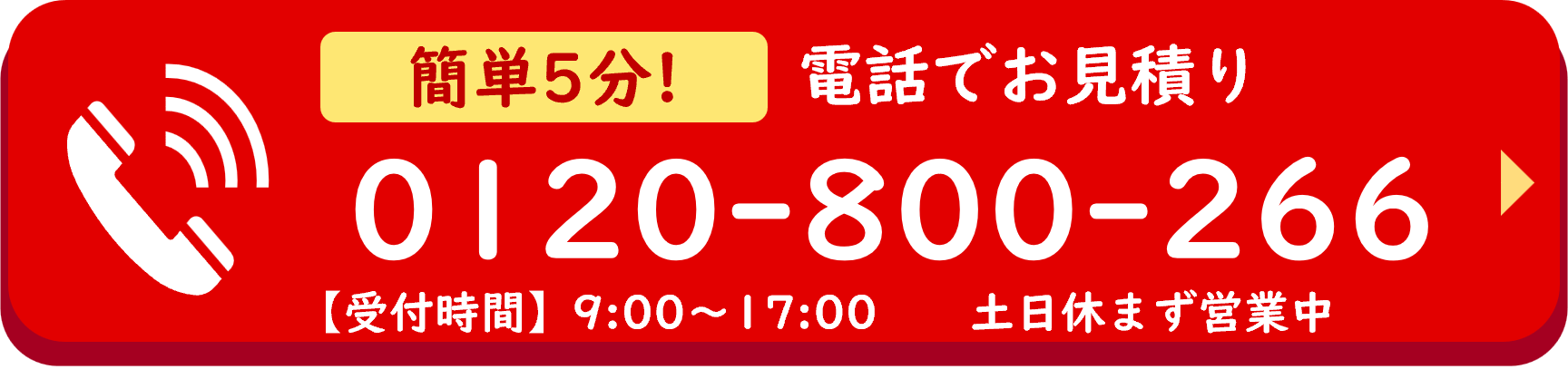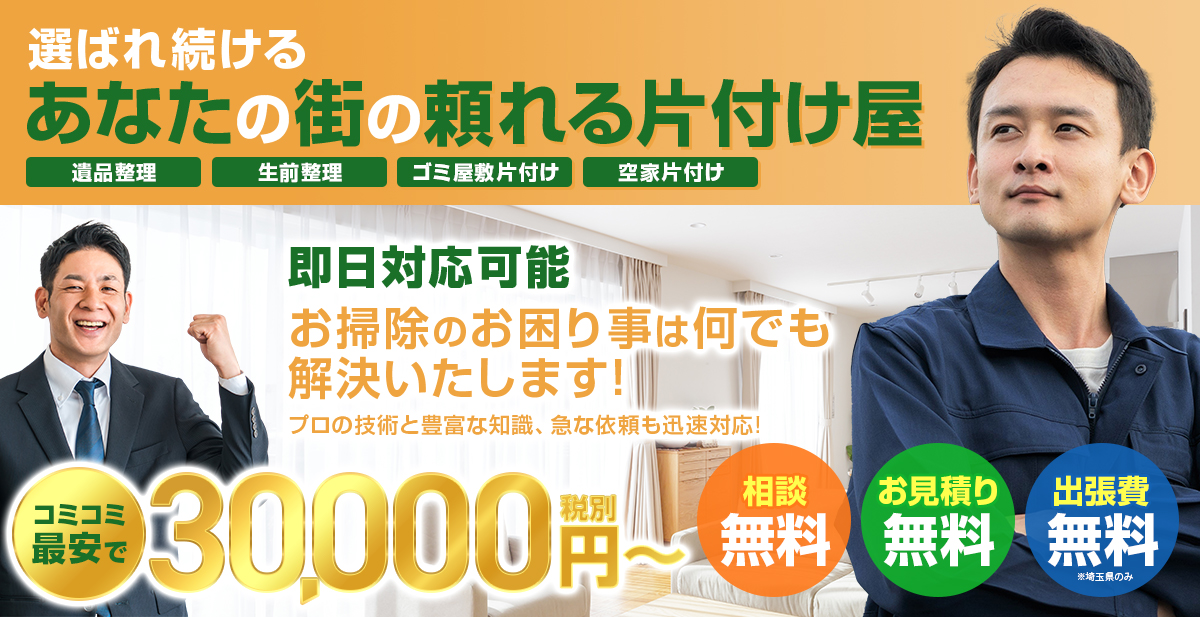
1.遺品整理業者を見極めるポイントと費用や相続の関係

遺品整理を業者に依頼する際、「どこに頼めばいいのか?」、「費用は誰が負担するのか?」など、さまざまな疑問や不安がつきものです。
特に、故人様の大切な遺品を扱う業者選びは、心身の負担を減らすためにも非常に重要です。
悪質な業者に騙されないための優良な業者を見極めるポイントや、知っておきたい遺品整理の費用負担と相続の関係について、分かりやすく解説します。
心から納得できる遺品整理のために、ぜひご一読ください。
1-1.優良な遺品整理業者を見極めるポイント「見積もり無料」「追加料金なし」は必須
遺品整理は信頼できる業者に依頼したいもの。
しかし、残念ながら一部には高額な追加請求をしたり、不法投棄をしたりする悪質な業者も存在します。大切な遺品を安心して任せられる優良な業者を見極めるために、必ず確認したい3つのポイントを解説します。
料金トラブルを避けるために最も重要なのが、見積もりの取り方です。
多くの業者が「見積もり無料」を掲げていますが、その内容をしっかり確認しましょう。

電話やメールだけでなく、必ず現地を訪問して詳細な見積もりを無料で出してくれる業者を選びましょう。
現場の物量や搬出経路を確認せずに提示された金額は、後から「想定より荷物が多かった」などの理由で追加料金が発生する原因になります。
また、見積書を受け取ったら、「追加料金は一切かかりません」という一文が記載されているか、担当者に直接確認することが不可欠です。
作業内容の内訳が「一式」と大雑把に記載されているのではなく、項目ごとに細かく明記されているかも信頼できる業者か判断する材料になります。
1-2.必要な許認可(一般廃棄物収集運搬業許可など)を持っているか?
| 許認可・資格の種類 | 内容 |
| 一般廃棄物収集運搬業許可 | 家庭から出るごみ(一般廃棄物)を収集・運搬するために市区町村から受ける許可。遺品整理において最も重要な許可です。自社で保有していない場合は、許可を持つ業者と提携しているか確認が必要です。 |
| 古物商許可 | 遺品を買取・販売するために都道府県の公安委員会から受ける許可。買取サービスを希望する場合は必須です。 |
| 遺品整理士など民間資格 | 一般財団法人遺品整理士認定協会などが認定する民間資格。法的な効力はありませんが、専門知識やコンプライアンス意識を持つスタッフが在籍している目安になります。 |

遺品整理で出た家庭ごみを収集・運搬するには、法律で定められた許認可が必要です。
無許可の業者に依頼すると、回収された遺品が不法投棄されるリスクがあり、最悪の場合、依頼主が責任を問われる可能性もゼロではありません。
業者の公式サイトなどで、以下の許認可や資格を保有しているか必ず確認しましょう。
1-3.口コミや実績が豊富か?
実際にその業者を利用した人の声は、信頼性を判断する上で非常に参考になります。
業者の公式サイトに掲載されている「お客様の声」だけでなく、Googleマップの口コミや遺品整理業者の比較サイトなど、第三者が運営するプラットフォームの評価も確認しましょう。

良い評価だけでなく、万が一悪い評価があった場合に、業者がどのように対応しているか(真摯な返信があるかなど)もチェックすると、その業者の姿勢がわかります。
また、公式サイトに具体的な作業事例(ビフォーアフターの写真、作業内容、料金、作業時間などが明記されたもの)が豊富に掲載されていれば、経験豊富な信頼できる業者である可能性が高いと言えるでしょう。
2.遺品整理の費用負担は誰がする?相続との関係
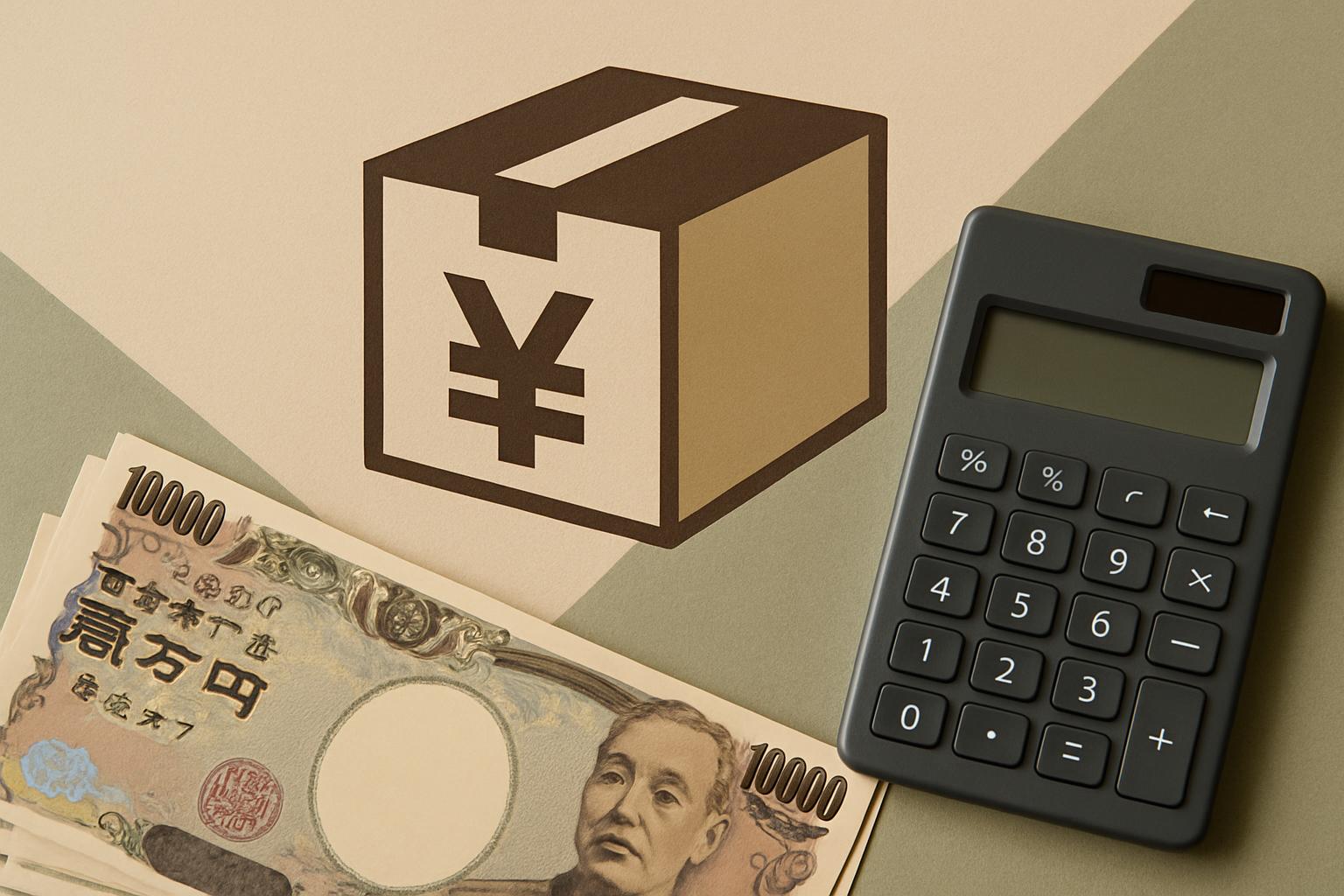
遺品整理を進める上で、「この費用は一体誰が支払うのだろう?」という疑問は多くの方が抱くものです。
故人の財産や親族間の関係にも関わるため、事前に正しい知識を持っておくことがトラブル回避につながります。
ここでは、遺品整理の費用負担者と相続の関係について詳しく解説します。
2-1.原則として費用は「相続人」が負担する
| 順位 | 法定相続人 | 備考 |
| 常に相続人 | 配偶者 | 常に他の順位の相続人と共に相続人となります。 |
| 第1順位 | 子(子が亡くなっている場合は孫) | 子が一人でもいる場合、第2順位以下の人は相続人になりません。 |
| 第2順位 | 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母) | 第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) | 第1順位・第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。 |
例えば、故人に配偶者と子がいれば、その両者が相続人となり、費用を負担する義務を負います。

遺品整理にかかる費用は、原則として故人の財産を相続する「法定相続人」が負担します。
遺品整理は、相続財産を確定させるために必要な行為と見なされるためです。
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことで、以下の通り順位が決まっています。
2-2.相続人が複数いる場合の費用分担方法

相続人が複数いる場合、遺品整理にかかる費用の分担方法については、法律で明確に定められているわけではありません。
これは、各家庭の事情や相続財産の内容が多岐にわたるため、一律のルールを設けることが難しいためです。
そのため、費用分担に関するトラブルを避けるためにも、相続人全員で話し合い、合意の上で決めるのが一般的です。
主な分担方法には、以下のようなものが挙げられます。
2-3.遺産分割協議で決める

最も一般的な方法です。相続人全員が集まり、遺産の分け方とあわせて遺品整理費用の負担割合についても話し合って決定します。
例えば、「長男が多く遺産を相続する代わりに、費用も全額負担する」といった柔軟な取り決めが可能です。
2-4.法定相続分に応じて分担する
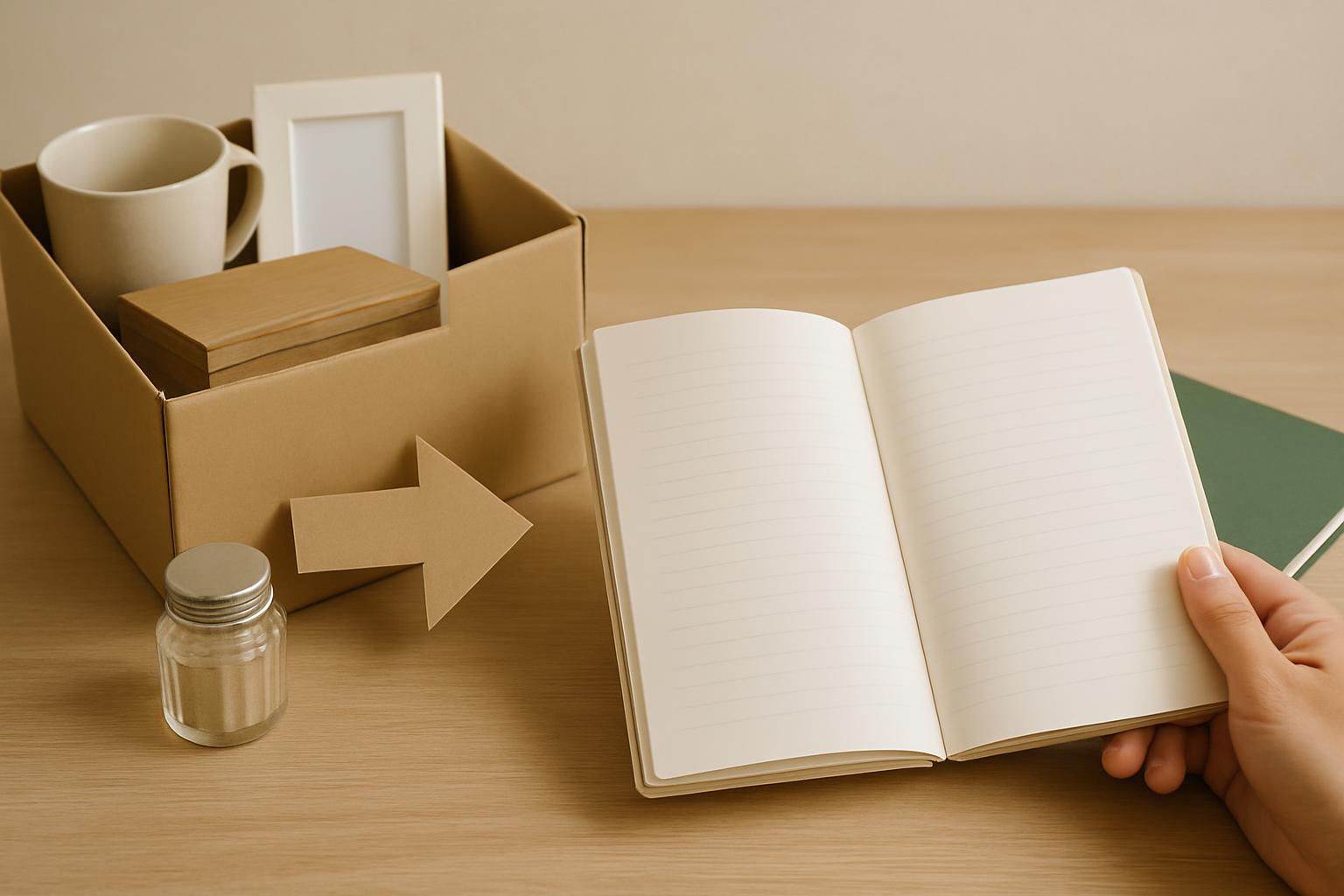
この方法は、法律で定められた相続割合(法定相続分)に基づいて遺品整理の費用を分担するため、最も公平な方法の一つとして広く用いられています。
誰がどれだけの費用を負担するかが明確になるため、相続人同士の認識のズレや、感情的な対立を防ぐことができます。
これにより、遺産分割協議をスムーズに進める上でも有効であり、後々の人間関係のトラブルを未然に防ぐという大きなメリットがあります。
特に、相続財産の総額が大きく、相続人が多いケースでは、公平な分担方法として非常に適しています。
2-5.代表者が立て替えて遺産から精算する

相続人のうちの一人が代表して費用を立て替え、後日、故人の預貯金などの相続財産から精算する方法です。
支払いをスムーズに進められますが、必ず事前に他の相続人全員の同意を得ておくことが重要です。
3.費用は故人の遺産(相続財産)から支払える?
はい、遺品整理の費用は故人の遺産(プラスの財産)から支払うことが可能です。
葬儀費用などと同じく「相続に関する費用」として扱われ、故人の預貯金などから支出することが認められています。

ただし、故人の銀行口座は死亡が確認されると凍結されてしまうため、引き出すには相続人全員の同意書や戸籍謄本などの書類が必要になります。
手続きに時間がかかる場合もあるため、前述の通り、一旦誰かが立て替えて後で精算するケースも少なくありません。
4.【注意】相続放棄をする場合の費用負担
故人に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続人は「相続放棄」を選択することがあります。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという手続きです。
相続放棄をした人は、法的には相続人ではなくなるため、遺品整理の費用を支払う義務も原則としてなくなります。

しかし、ここで非常に重要な注意点があります。
相続放棄を検討している場合、勝手に故人の遺品を売却したり、形見分けとして持ち出したりしてはいけません。
そうした行為は、財産を相続する意思がある「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
遺品整理業者に依頼する場合も、費用を故人の財産から支払うと単純承認とみなされるリスクがあるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:遺品整理の賢い進め方
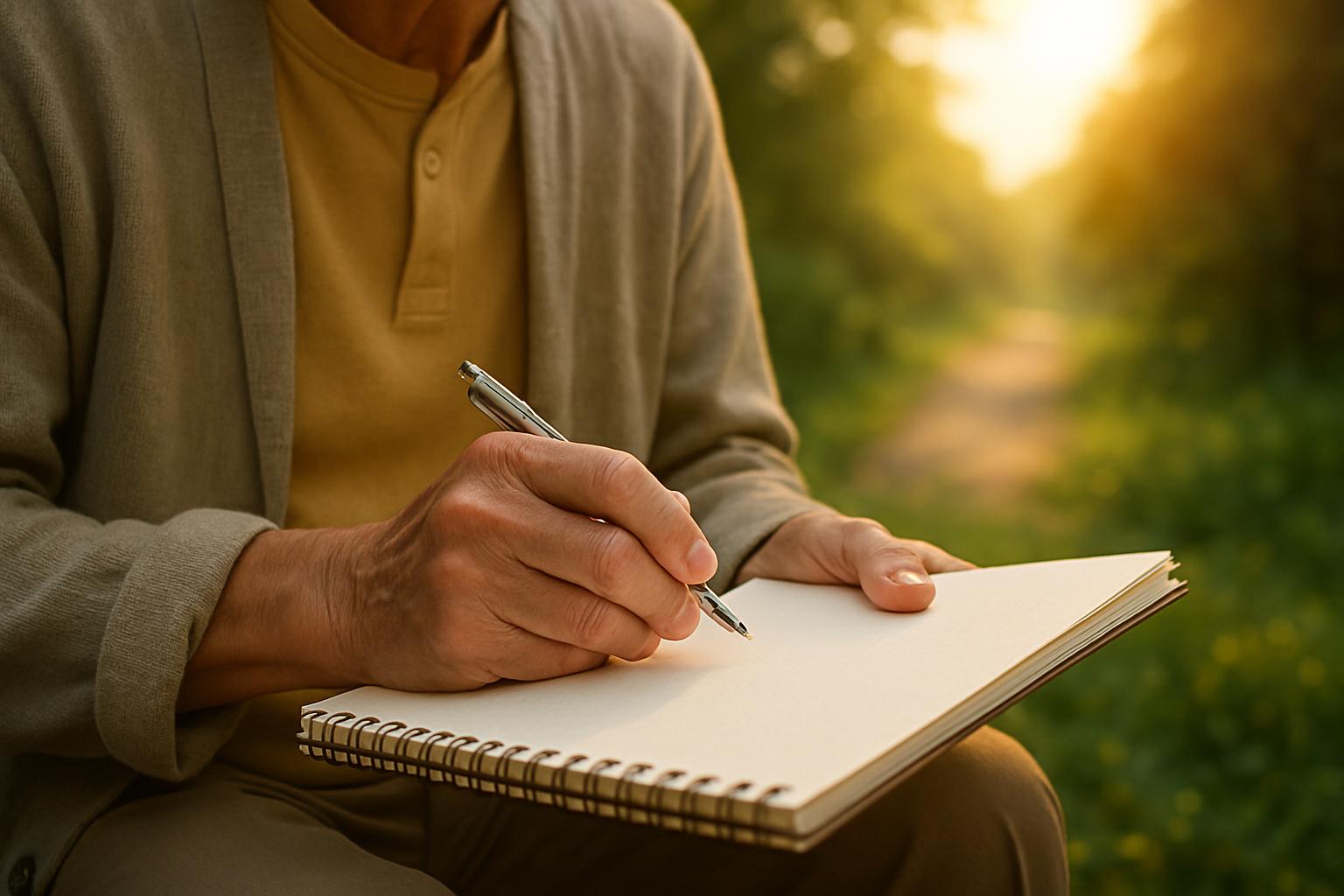
遺品整理の費用は、サービス内容や物量、そして業者選びによって大きく変わります。
安心して依頼するためには、優良な遺品整理業者を見極めるポイントを理解し、複数の業者を比較検討することが最も重要です。
また、不用品をリサイクル・リユースしたり、事前に自分で片付けを行ったりすることで、費用を抑えることが可能です。
私たちは、お客様の負担を少しでも減らせるよう、不用品の買取や再販にも力を入れています。
さらに、遺品整理費用の支払い者や、相続との関係性についても、お客様の状況に合わせてアドバイスいたします。遺品整理に関するご質問やご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
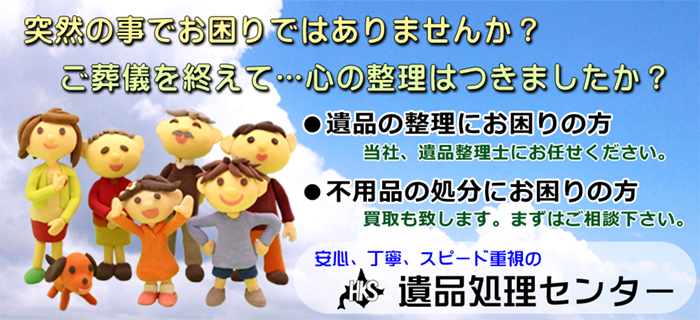

【 お問い合わせ 】
遺品や残置物のことでお困りなら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
※上記のボタンをタップしていただければ、それぞれの窓口につながります。